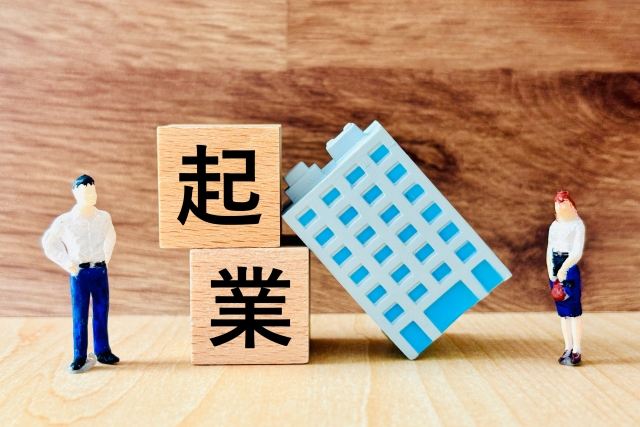皆さん、こんにちは!大村市の「初心者向け不動産学校」校長代理のハッピーです。

今日の「ハッピーの世の中ウォッチング」は、ビジネス界でまことしやかに囁かれている、
ある「怖い噂」について深掘りしてみたいと思います。
これから起業を考えている方や、経営者の方なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「起業して10年後に生き残っている会社はたったの1割(生存率10%)」という話を。
「えっ、9割も失敗するの?そんなに危険なの?」と不安になってしまいますよね。
でも、安心してください。結論から申し上げますと、この数字は「都市伝説」に近いものです。
今日は公的なデータをもとに、本当の生存率と、なぜそんな噂が生まれたのかを紐解いていきましょう。
実際の生存率はもっと高い
まず、実際のデータを見てみましょう。
日本の公的な統計である「中小企業白書」や「帝国データバンク」の調査データを見ると、
全く違う景色が見えてきます。
個人事業主を含む中小企業の生存率の目安は以下の通りです。
1年後の生存率:約95%
3年後の生存率:約88%
5年後の生存率:約81%
10年後の生存率:約70%程度
いかがでしょうか。「10年で9割が消える」どころか、
実際には「10年経っても6〜7割以上の企業が存続している」のが日本の現状です。
日本企業は世界的にも見ても、一度創業すると粘り強く続く傾向があるのです。
なぜ「生存率10%」という都市伝説が生まれたのか?
では、なぜこれほどまでに実態と乖離した数字が広まってしまったのでしょうか。
理由は大きく分けて3つ考えられます。
「ベンチャー企業」と「一般企業」の混同 この低い生存率は、
急成長を目指すITベンチャーやスタートアップ企業に限定した古いデータや、
海外の激しい競争環境のデータが、一般の飲食店や建設業、不動産業など
すべてに当てはめられて語られてしまった可能性があります。
「廃業」と「倒産」の混同 会社がなくなる理由は
「倒産(借金で首が回らなくなる)」だけではありません。
経営者が高齢化して引退したり、黒字だけど別の事業をするために畳んだりする
「前向きな廃業」も数多くあります。
これらをすべて「失敗」としてカウントすると、数字は悪く見えてしまいます。
危機感を煽るためのレトリック コンサルタントやセミナーなどで、
「起業は甘くない」と警告するため、あるいは集客のために、
あえて衝撃的な数字が引用され続け、それが定着してしまったという側面もあります。
失敗する企業のリアルな特徴
とはいえ、10年で約3割の企業が市場から退出しているのも事実です。
失敗してしまう企業には、データ上いくつかの傾向が見られます。
資金繰りのショート 赤字だから潰れるのではなく、手元の現金がなくなると会社は終わります。
売上の入金サイトと支払いのタイミングのズレを把握していないケースが多々あります。
販売不振の放置 中小企業庁のデータによると、倒産理由の断トツ1位は「販売不振」です。
市場のニーズが変わっているのに、過去の成功体験に固執して商品やサービスを
変えられない硬直性が命取りになります。
小回りが利かなくなる 組織が大きくなるにつれて決定スピードが遅くなり、
変化の激しい時代についていけなくなることも要因の一つです。
まとめ
「10年で9割潰れる」という言葉に過度に怯える必要はありません。
日本の土壌では、しっかりと準備をし、お客様に対して誠実な商売を続けていれば、
多くの企業が生き残ることができます。
大切なのは、都市伝説に惑わされず、目の前の数字(キャッシュフロー)と
お客様の声を大切にすること。
私たちも、長く愛される「出張ふどうさん」でありたいと改めて思いました。
皆さんの挑戦が、長く実りあるものになりますように、ここ大村市から応援致します!
それでは、また次回の「ハッピーの世の中ウォッチング」でお会いしましょう。
校長代理のハッピーでした!
出典元・参考文献
中小企業庁「中小企業白書(2011年版・2017年版)」における企業の生存率データ
日経ビジネス「ベンチャー企業の生存率」関連レポート
帝国データバンク「全国企業倒産集計」